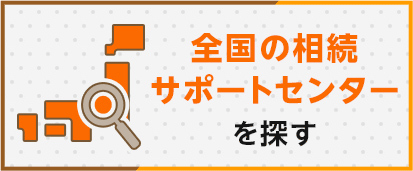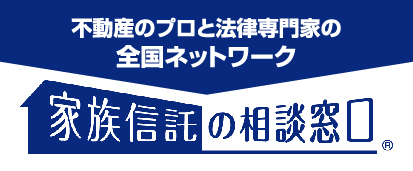[ 空室でお困りのオーナー様 ]空室改善のご提案・サポートをいたします
[ 空室でお困りのオーナー様 ]
空室改善のご提案・サポートをいたします

都市部では物価や人件費の高騰にともない、賃料の上昇が話題になることが増えているようです。一方、地方や郊外では「まずは空室を埋めたい」というのが実情で、家賃を上げるどころではないというオーナーも多いでしょう。ただ、どのエリアであっても共通するのは、「入居者とどう向き合うか」が経営の質を左右するということ。今回は、行き過ぎた家賃改定で世間を騒がせたある事例を通じて、改めてオーナーの責任と姿勢を考えてみたいと思います。
相場の2倍以上の家賃改定にSNSは騒然
東京・板橋区の築40年以上の賃貸物件で、もともと月額7万2500円だった家賃を、いきなり19万円に引き上げるという通知が入居者に届いたことがニュースとなりました。対象は30㎡程度のワンルーム。周辺相場より多少安い水準ではありましたが、突然の“相場の2倍以上”の家賃改定に、SNSでも「嫌がらせでは?」「合法なのか?」といった声が飛び交いました。
民泊運営のための退去を目的とした改定か
背景としては、最近オーナーが外国籍の方に変わったことや、エリアの賃料上昇があると報じられています。確かに、修繕費の高騰や管理コストの上昇を理由に賃料見直しを検討するのは正当な経営判断のひとつです。そして、借地借家法に基づき、周辺相場や経済事情の変化を根拠とした賃料の「増減額請求」は認められています。
ただし、実際に値上げを実現するには入居者の合意が不可欠です。合意が得られない場合、オーナー側が裁判を通じて妥当な金額を主張するしかありません。そして、こうした裁判で過去に認められてきたのは、現行賃料と相場の「中間水準」に落ち着くことが大半であり、相場の倍以上という金額がそのまま通ることは、ほぼありません。
こうした極端な値上げは、実質的には「退去」を目的としていることが多く、今回の物件でも無許可で民泊運営が行われている可能性が指摘されています。さらに、退去に応じない入居者に対してエレベーターを止めるなどの嫌がらせ行為も報じられ、問題は深刻です。
法律上、仮にエアコンが使用できない場合でも、賃料減額はおおむね10%程度。共用部であるエレベーターの場合、その影響はより小さいとされ、入居者が泣き寝入りになるケースもあります。こうした一連の行為は、オーナーの信頼を著しく損なう結果となります。
入居者からの信頼が資産価値を支える
収益性を高めたいという思いは、エリアを問わず多くのオーナーが共有しているはずです。特に地方では、空室率の高さや家賃下落圧力に直面しているケースも多く、より一層の工夫と努力が求められます。しかし、入居者の信頼を無視した短期的な利益追求は、結果的に空室を増やし、地域での評判を落とし、長期的には収益悪化を招きかねません。
不動産オーナーにとって、物件は大切な資産です。ただ、その資産の価値を支えているのは、そこに「住む人」の存在であるということを忘れてはならないのです。
地方であれ都市部であれ、「安心して住み続けられる環境を提供する」姿勢こそが、経営の土台。どんな状況でも、「入居者に選ばれるオーナー」であり続けることが、安定経営への近道なのではないでしょうか。